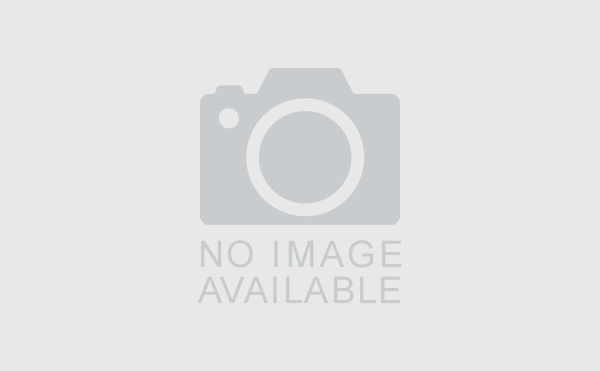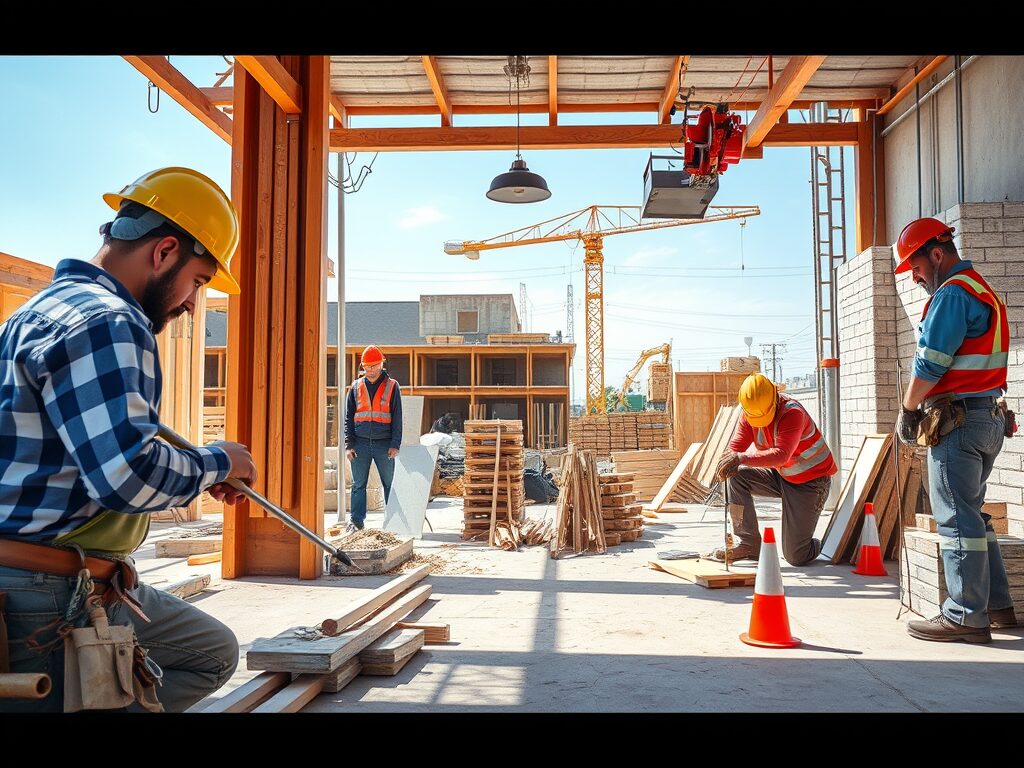
建設業許可とは?
建設業許可は、一定の規模以上の工事を行うときに必要な許可です。これがないと、多くの公共工事や大きな民間工事ができなくなってしまいます。個人事業主や中小企業の方にとっても、信用や受注の面で大きな影響があるため、早めの取得が大切です。
なお、軽微な工事(500万円未満の工事や、木造住宅で延べ面積150㎡未満など)については許可が不要なケースもあります。
許可が必要なケースとは?
建設工事で「500万円以上(税込)の工事」または「建築一式工事で1,500万円以上(税込)または延べ面積150m2以上の木造住宅」の場合、建設業許可が必要です。
建設業の29業種一覧
建設業許可は、以下の29業種ごとに分かれています。業種ごとに許可が必要なので、実際の工事内容に応じて取得することになります。
一式工事(2種類)
- 土木一式工事:道路、橋、上下水道など土木構造物をまとめて施工する工事
- 建築一式工事:建物を新築・改修・増築する際の全体的な工事
専門工事(27種類)
- 大工工事:木造建物の骨組みを作る工事
- 左官工事:壁や床にモルタルや漆喰などを塗る工事
- とび・土工・コンクリート工事:足場の設置や地盤の掘削・埋戻しなど
- 石工事:石材を使った構造物や装飾の工事
- 屋根工事:屋根の葺き替えや新設などの工事
- 電気工事:配線や照明、電源設備の設置工事
- 管工事:給排水や冷暖房などの配管工事
- タイル・れんが・ブロック工事:外壁や内装に使用される素材の施工
- 鋼構造物工事:鉄骨などを用いた構造物の工事
- 鉄筋工事:鉄筋コンクリート建物に使う鉄筋の組立て工事
- 舗装工事:道路や駐車場などの舗装作業
- しゅんせつ工事:河川や港湾の底にたまった土砂を除去する工事
- 板金工事:建築物の屋根・外壁などに金属板を取り付ける工事
- ガラス工事:窓ガラスなどの設置・交換工事
- 塗装工事:建物や構造物の塗装全般
- 防水工事:雨漏りなどを防ぐ防水処理
- 内装仕上工事:クロス貼りや床仕上げなど室内の最終仕上げ
- 機械器具設置工事:大型設備や機械の据付け工事
- 熱絶縁工事:断熱材の設置による温度調整工事
- 電気通信工事:通信設備の設置(LAN、電話線など)
- 造園工事:庭園や公園の設計・施工
- さく井工事:井戸の掘削や整備
- 建具工事:ドアや窓などの取り付け・修繕
- 水道施設工事:上下水道の整備工事
- 消防施設工事:スプリンクラーや消火器などの設置
- 清掃施設工事:ごみ処理施設などの建設工事
- 解体工事:建物の取り壊し工事
許可取得の注意点
- 複数業種の取得が可能:複数の工事を行うなら、それぞれに対応する許可が必要です。たとえば、塗装と防水工事の両方を手がける場合は、両方の許可が必要になります。
- 更新が必要:建設業許可には有効期限があり、5年ごとの更新手続きが求められます。忘れると業務停止になることもあるため注意が必要です。
- 専任技術者などの人材要件もあり:許可取得には、実務経験や国家資格などを持った技術者が必要です。業種に応じた人材の確保もポイントです。
まとめ
建設業許可は29業種に分かれており、どの業種に該当するかをしっかり把握して取得することが大切です。許可があれば、受注のチャンスも広がり、信頼性もアップします。まだ取得していない方は、早めの準備をおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q. どの業種の許可を取ればいいかわかりません。
A. 実際の工事内容をもとに判断する必要があります。不安な場合は行政書士に相談しましょう。
Q. 一つの会社で複数の許可を取ることは可能ですか?
A. はい、可能です。業務内容に応じて必要な業種の許可を複数取得できます。
Q. 許可取得にどのくらいの期間がかかりますか?
A. 書類が揃ってから、通常1~2ヶ月程度が目安です。
Q. 建設業許可の取得にかかる費用はどれくらいですか?
A. 許可の種類や手続き方法によって異なりますが、申請料や行政書士報酬を含めて20万円〜50万円程度が一般的です。
関連記事・内部リンク

行政書士・宅地建物取引士・認定IPOプロフェッショナル
中小・小規模建設業者様の建設業許可に関するご相談、お手伝いをしています。
最初はメールかお電話でお問い合わせください。
許可取得後の許可の管理もさせていただいております。